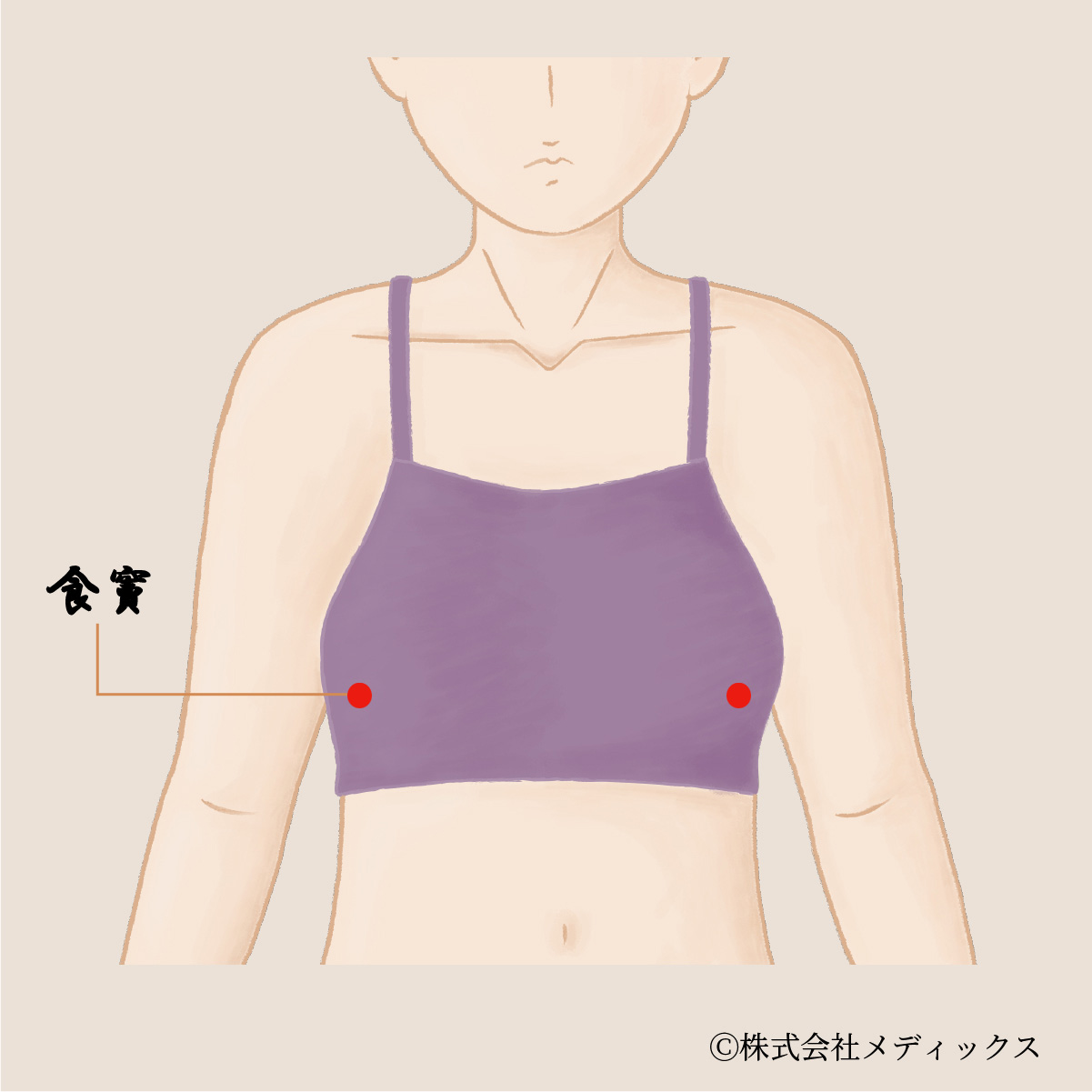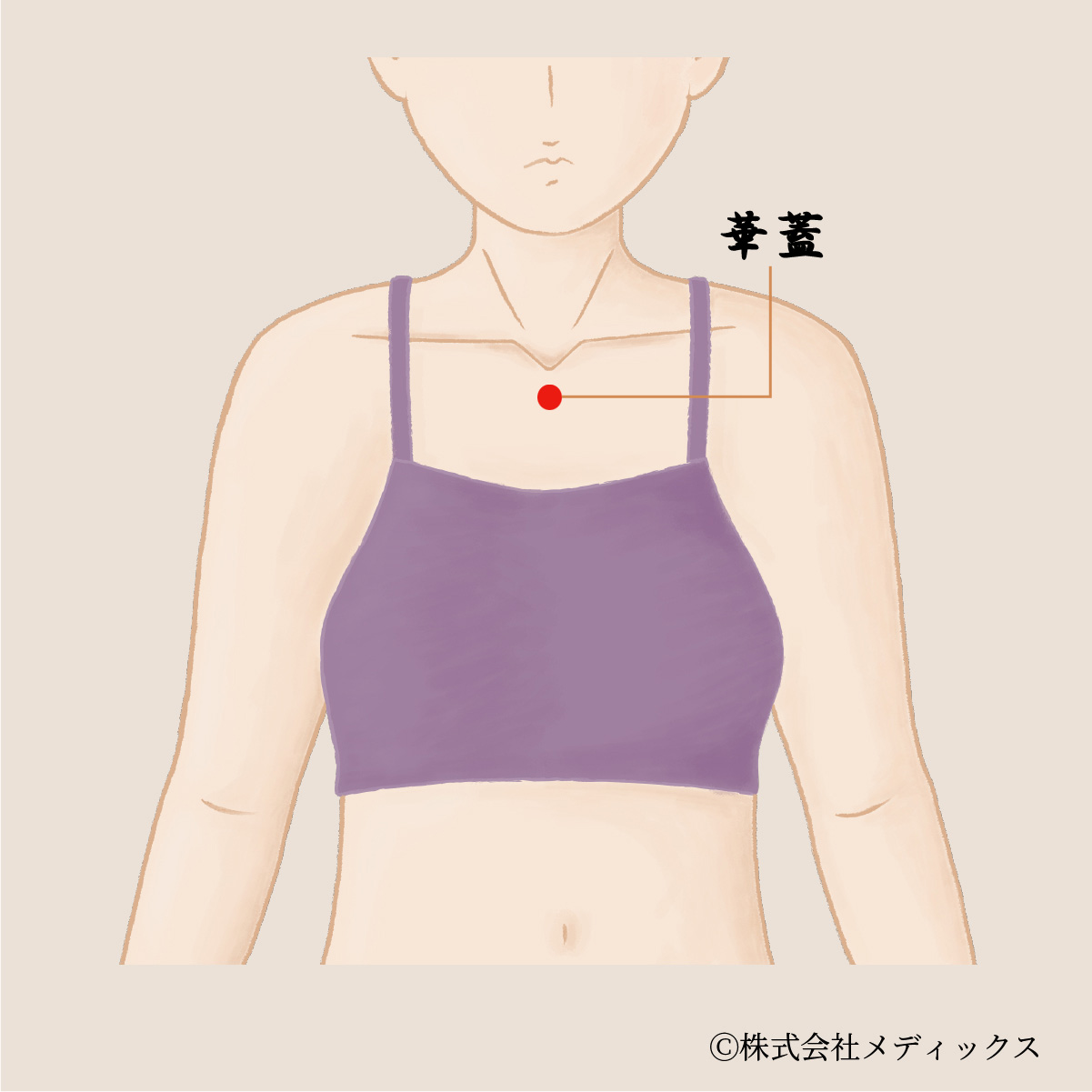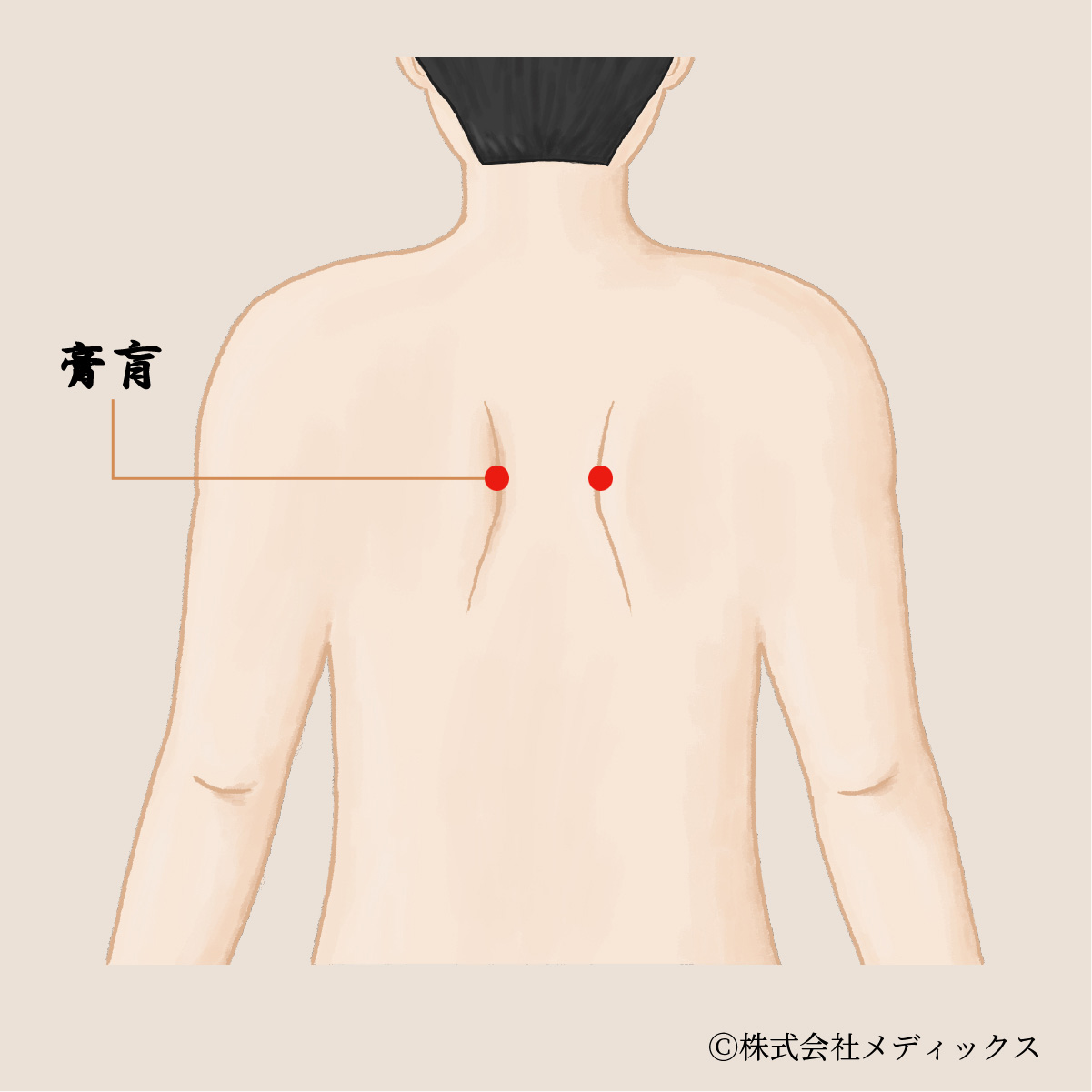【懸鐘】下半身の巡りと骨の強さに働きかける胆経のツボ

目次
目次がありません
懸鐘(けんしょう)とは
懸鐘は、足の少陽胆経に属する経穴で、外くるぶしの上約3寸、腓骨の前縁に位置する。
「懸」は“吊るす”、“鐘”は“骨の中の空洞”を指すことから、骨や髄に関わるツボとされ、東洋医学では骨の衰えや下半身の虚弱に影響を与えるポイントとされている。
また、胆経上にありながら骨髄との関連が強く意識されている特殊なツボでもある。
効果と応用
主に、足のだるさや冷え、下半身の疲労感に対して使われる。
さらに、骨粗鬆症や脚の衰え、ふらつき、健忘や物忘れといった症状にも応用されることがある。
「骨は腎に属す」とされる東洋医学の考え方から、腎精(生命エネルギー)を補う目的で使われるケースもある。
主な効果
懸鐘は、足の巡りを促進しながら、骨や関節の安定をサポートする作用がある。
特に、高齢者や体力低下が気になる人に対して、足腰の衰えを防ぐ補助的なケアとして用いられる。
また、胆経は精神面にも関与するため、気分の浮き沈みや集中力の低下に対しても安定化を図る効果が期待される。
注意点
やや骨に近い位置にあるため、指圧する際は力を入れすぎず、周囲をゆっくり探るように刺激するのが望ましい。
腓骨神経との距離も比較的近いため、ピリピリとした違和感がある場合はすぐに刺激を中止すること。
また、強い冷えや痛みがある場合には、まず温熱刺激からはじめる方が安全。
日常生活での活用法
座ったまま、または寝転んだ状態で、外くるぶしから指3本分上の外側を手のひらで包むように温めると効果的。
また、足湯やカイロを使ってこの部分をじんわり温めるだけでも、下半身全体が軽くなるような感覚が得られる。
足のだるさを感じたときには、懸鐘周辺を中心に軽くさするようなマッサージを行うと巡りが整いやすい。
現代医学からの評価
懸鐘の位置は、腓骨筋・腓骨骨膜・浅腓骨神経の付近にあたり、ふくらはぎの外側の循環や神経の通り道に関与している。
この部位の血流改善や筋緊張の緩和は、足の疲労感や感覚異常のケアに有効とされ、リハビリや理学療法の一部でも扱われることがある。
また、「骨と髄」を意識した養生法と結びつけやすく、東西医学の融合的な視点から見直されているツボのひとつ。